
米国(アメリカ)の長短金利差(長期金利と短期金利の差)で最も注目される10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差の最新データを速報で掲載しています。この長短金利差がマイナスとなれば(逆イールド)これまで100%の確率で景気後退入りしたことから、景気後退を予兆するシグナル指標としても有名です。逆イールド発生時はチャートでチェックできるようにしていますので確認して下さい。株価(NYダウ・ナスダック・S&P500)との比較チャートも掲載しています。

AIによる長短金利差(米国10年債と2年債)の重要度評価
米国2年債はFRBの金融政策に敏感に反応し、10年債は市場の長期的な成長期待やインフレ期待を反映する。米国10年債と2年債の金利差は、景気後退の兆候を示す先行指標として広く認識されている。特に、過去の景気後退前に一貫して逆イールドが発生しており、信頼性が高い。ただし、10年債と3カ月債の金利差に比べて、予測精度が若干劣る。また、10年債と3カ月債の金利差と比べると、逆イールドが発生しても景気後退までのリードタイムが長めな傾向がある。金利差が縮小または逆転しても、短期的な市場のゆがみが影響を与えることがあり、単独では判断材料として不十分な場合があるため、 ISM製造業指数や失業率など他の経済指標との併用が推奨される。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
- AIによる長短金利差(米国10年債と2年債)の重要度評価
- チャート(米国10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差)
- 米国10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差の関連指標
- [速報] 最新データ|米国10年債と2年債の長短金利差の時系列(historical data)
- 米国10年国債利回りと2年国債利回りの計算式
- セントルイス連銀公表の長短金利差について
- 長短金利サイクルと銀行の収益・貸し出し・不良債権の傾向
- 逆イールドと銀行株の下落
- 長短金利差がマイナスとなれば、100%の確率で景気後退入り!
- 逆イールドで景気後退入りが100%!チャートで確認しよう!
- 利上げと逆イールド、株価への影響は?
- なぜ逆イールド発生とリセッション入りにはタイムラグ(時間差)がある?その理由
- 逆イールドの期間と景気後退期間の関係は?同期間になりやすい
- FOMCを境に長短金利差はどう動いた?
チャート(米国10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差)
(日次)米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差のチャート
米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差の推移を示したチャートです。
(日次)米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差とNYダウのチャート
米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差とNYダウの推移を示したチャートです。
(日次)米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差とナスダックのチャート
米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差とナスダック総合指数の推移を示したチャートです。
(日次)米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差とS&P500のチャート
米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差とS&P500の推移を示したチャートです。
(月次)米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差の長期チャート
米国10年国債利回りと2年国債利回りの長短金利差の長期の推移を示したチャートです。米国の景気後退期との比較チャートにしています。
長短金利差(米10年債-2年債)を表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 日次チャートのピンク色の背景の期間は逆イールドが発生している期間です。
- NYダウ・ナスダック総合指数・S&P500は終値を反映しています。
- 月次チャートのデータは、それぞれ月末終値を掲載しています。
- 月次チャートの灰色の囲みの期間が米国の景気後退期(リセッション期)です。米国の景気後退期間の解説と推移は「景気後退期間(米国・アメリカ)」のページを参照してください。
米国10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差の関連指標
10年国債利回りと3カ月国債利回りの利回り差
米国の長短金利差(長期金利と短期金利の差)で当ページで掲載している10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差の次に注目される10年国債利回りと3カ月国債利回りの利回り差の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差と10年国債利回りと3カ月国債利回りの利回り差のどちらを重視すればいいかの解説や、逆イールドと景気後退の見方、長短金利差とともにチェックした方がいい期待インフレ率や実質金利の見方の解説も、上記のページに記載しています。
米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジション
米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションは、以下のページで掲載しています。
逆イールド発生でより厳格化されやすい銀行の「貸出態度指数」
逆イールドでより厳格化されやすいのが銀行の貸出態度です。それを確認できるのが貸出態度指数です。その水準は景気後退(リセッション)の目安としても機能してきました。貸出態度指数の推移と解説は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|米国10年債と2年債の長短金利差の時系列(historical data)
| 日付 | 長短金利差 (10年-2年) |
|---|
長短金利差(米10年債と2年債)の解説
米国10年国債利回りと2年国債利回りの計算式
長短金利差(%)=米国10年国債利回り-米国2年国債利回り
セントルイス連銀公表の長短金利差について
当ページでは、米国(アメリカ)のセントルイス連銀公表の長短金利差の推移を掲載しています。これは、米財務省が公表している米国債のデータを基にセントルイス連銀が公表している長短金利差で、米国の長短金利差を見る場合はこれを見るのが基本ですが、米財務省の米国債のデータは実際に市場で取引されている市場利回りとは違います。各取引日の午後3時30分頃に取得した国債入札側の相場から米財務省のモデルを基に算出しているレート(推定値)です。これは、米財務省の判断で調整する権限があります。その点は把握しておいた方がいいですが、市場利回りと実際ほぼ同じで、FRB(連邦準備制度理事会)もこの長短金利差を見ていると公言しています。気にするレベルではないと思いますが、気になる方は実際に市場で取引されている市場利回りを参照してください。実際に市場で取引されている市場利回りは、以下のページで掲載しています。

長短金利サイクルと銀行の収益・貸し出し・不良債権の傾向
長短金利サイクル(長期金利と短期金利のサイクル)は、通常以下の3段階になる傾向があります。
- 第1段階は、FRB(連邦準備制度理事会)の利上げによって長期金利と短期金利が上昇、利上げを見越して長期金利はより上がりやすく、イールドカーブがスティープ化する段階です。この時、銀行の債券は含み損が膨らみやすくなります。
- 第2段階は、FRBの利上げが進んでくると、先んじて上昇している長期金利に短期金利が追い付き長短金利差が縮小、その後、短期金利が長期金利を追い抜いて逆イールドが発生します。銀行は短期でお金を調達して長期で運用するビジネスモデルですので、逆イールドになると利ざやが悪化します。この時、銀行は債券の含み損が膨らんで利ざやが悪化する、というダブルパンチの状況になります。この状況下で銀行不安等が起こりやすくなり、銀行が貸し出しを渋りやすくもなり経済や景気が悪化しやすくなります。
- 第3段階は、経済が悪化して伝統的な不良債権問題が発生しやすくなる段階です。貸出資産が劣化して不良債権化し、銀行の収益がさらに悪化します。銀行の資本が不足する可能性が出てきますので、銀行不安がさらに起こりやすい状況になります。この時、イールドカーブは利下げを織り込み始めますので、短期金利と長期金利は低下、短期金利は長期金利より低下し、短期金利が長期金利より低くなります。
逆イールドと銀行株の下落
長短金利差が逆イールドになれば逆ざやで銀行の収益が悪化するのは上記の通りですので、この状態の間は銀行株はほぼ上昇しないか大きく下落する傾向があります。銀行不安も起こりやすい状況が続き、利下げで金利が下がらない間は収益状況が厳しい状態が続きます。中小ほどその影響は大きくなりやすいです。大手も同様に影響があり、さらに破綻する中小を大手が救済するケースがあってもその負担が増す可能性が高まるので注意が必要です。短期金利が高いと負債が多い企業が苦しくなりますが、銀行はその筆頭といえます。
長短金利差がマイナスとなれば、100%の確率で景気後退入り!
当ページで掲載している米国の長短金利差(10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差)がマイナスとなった場合(逆イールドとなった場合)、これまで米国ではその後、100%の確率で景気後退期入りしていることから景気後退期入りを予兆するシグナルとしても有名です。
逆イールドで景気後退入りが100%!チャートで確認しよう!
当ページではチャートの欄で、1976年からの米国の長短金利差(10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差)の推移を掲載しています(セントルイス連銀公表分)。チャート上にグレー(灰色)で囲ってある期間が米国の景気後退期間です。
この長短金利差のマイナス(逆イールド)と景気後退入りの傾向と、今後の考察は以下のページを参照してください。
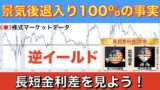
利上げと逆イールド、株価への影響は?
過去、この長短金利差はFRBの利上げの最終局面でマイナスとなり(逆イールド)、その後に景気後退期入りする傾向が100%出ています(利上げの最終局面でFF金利は天井)。この間の株価(S&P500)は、逆イールドの最終局面までは上昇しやすい傾向があり、景気後退期には下落、その後に上昇するパターンが多いです。
FF金利(米国の政策金利)は以下のページで掲載しています。

なぜ逆イールド発生とリセッション入りにはタイムラグ(時間差)がある?その理由
長短金利差で逆イールドが発生した場合、過去の傾向では100%の確率で景気後退期(リセッション)入りしてきました。そして、逆イールドが発生してから期間を空けてリセッション入りしている傾向もあります。つまり、逆イールドからリセッション入りまで時間差があるのです。この時間差はなぜ起こるのでしょうか?
通常、FRBが利上げをしても、企業や個人への利払いに影響が出るのは半年から1年程度かかるからです。すぐに影響は出ないのです。これはウィリアムズNY連銀総裁も利払いに影響が出るのは半年から1年程度かかると発言しています。さらに、景気がよくインフレが強い局面で利上げをするので、すぐにリセッション入りしにくいことも考えられます。また、実質金利も見ておいた方がよいでしょう。実質金利が低い状況では、景気はそうすぐに悪くなりにくいです。
米国の実質金利は、以下のページで掲載していますので参考にしてください。

逆イールドの期間と景気後退期間の関係は?同期間になりやすい
米国では逆イールドとなった後、100%の確率で景気後退期入りしていますが、その期間も特徴があります。過去の傾向では、逆イールドになっている期間と景気後退の期間がほぼ同じになりやすい傾向があります。逆イールドの期間が1年だとすれば、その後に訪れる景気後退の期間も1年程度になりやすいという傾向です。
FOMCを境に長短金利差はどう動いた?
米国の中央銀行制度の最高意思決定機関であるFRBが開催する米国の金融政策を決定する委員会「FOMC(連邦公開市場委員会)」を境に、長短金利差(米国10年国債利回りと2年国債利回り)はどう動いたのか?以下のページにチャートで掲載していますのでご利用下さい。
- 当ページは、米国の長短金利差(10年国債利回りと2年国債利回りの利回り差)の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「逆イールドになった場合の株価と景気・経済への影響」 - Source:Federal Reserve Bank of St.Louis
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity historical data&chart




